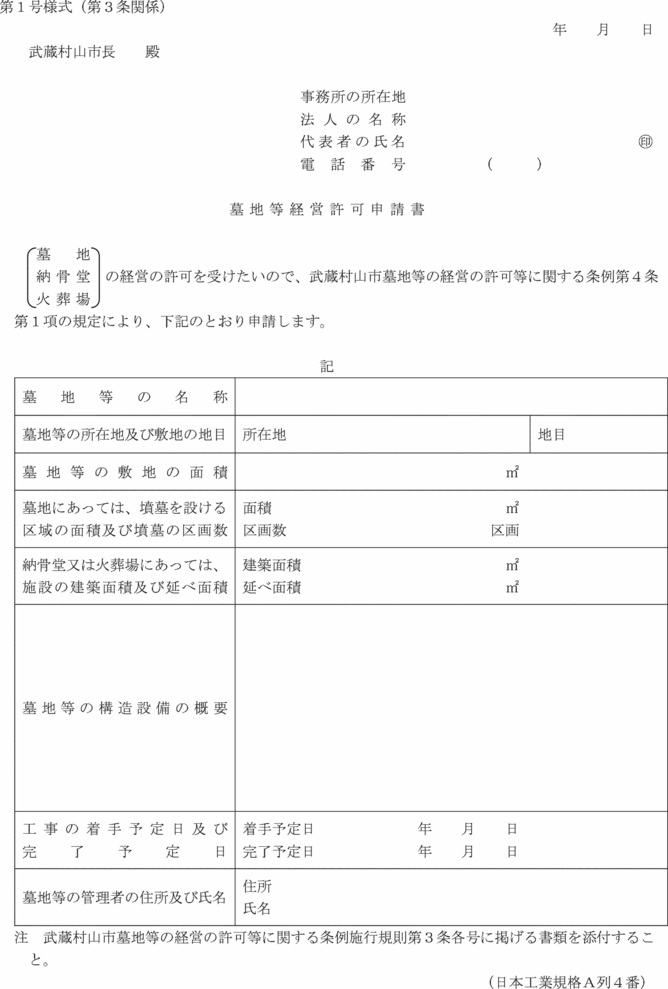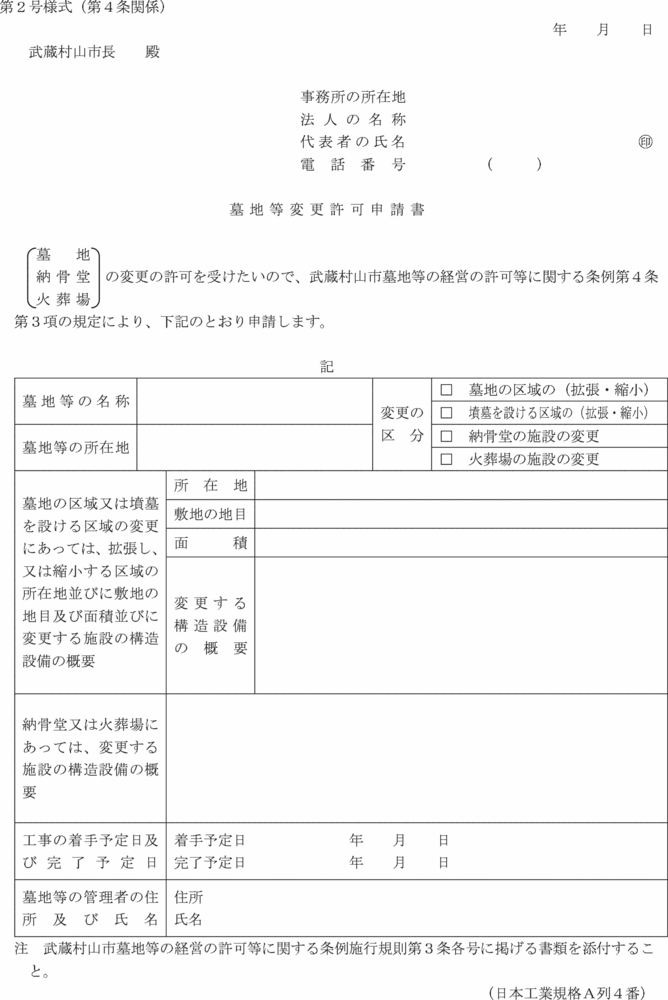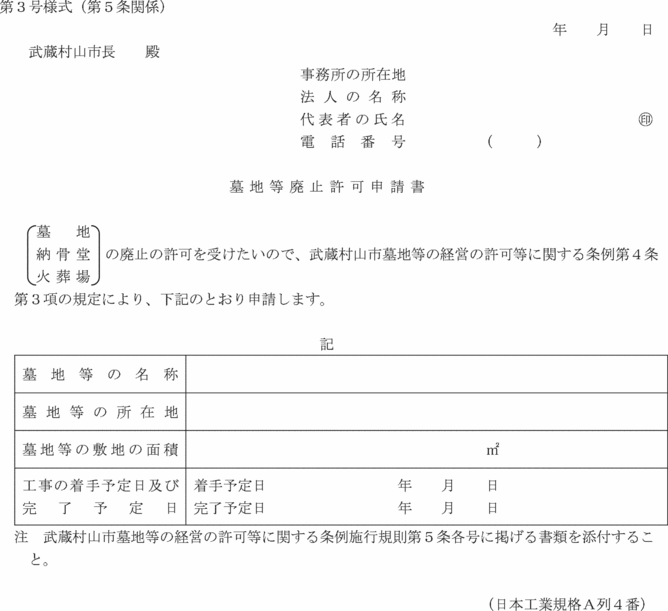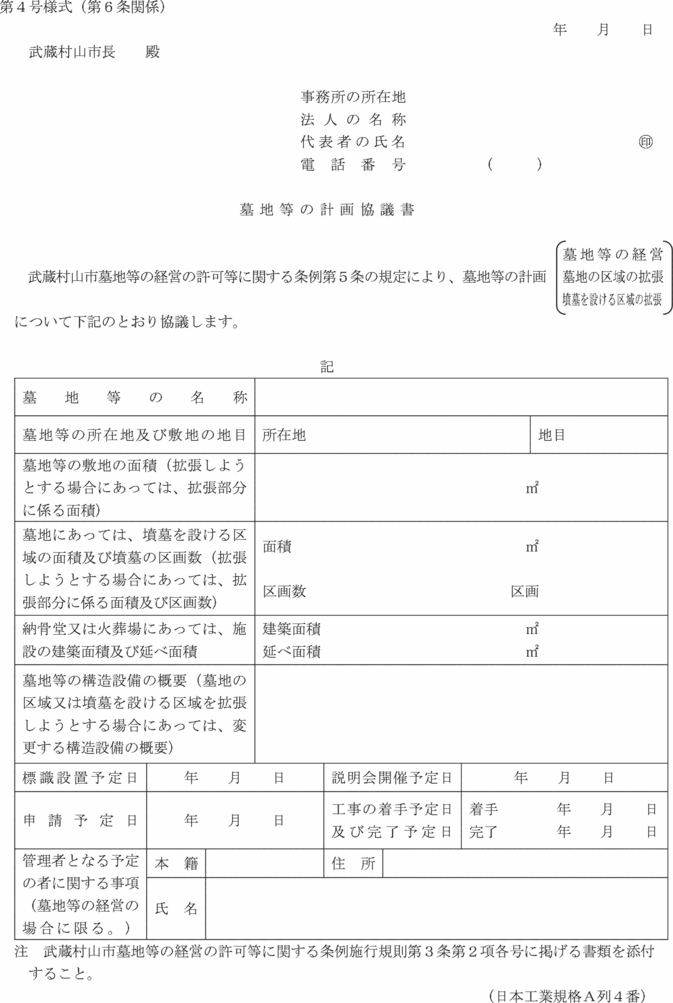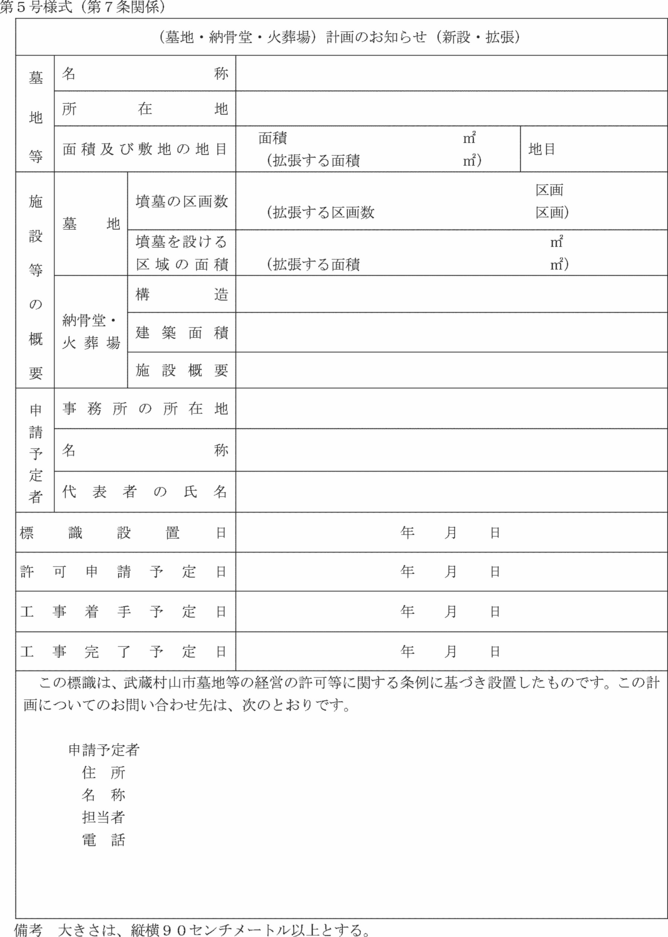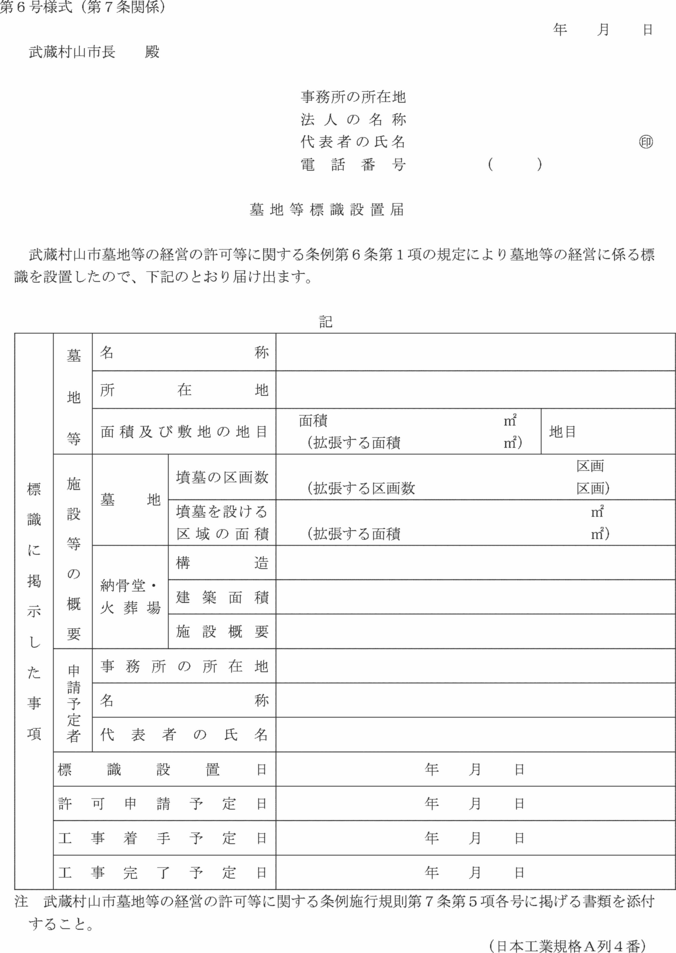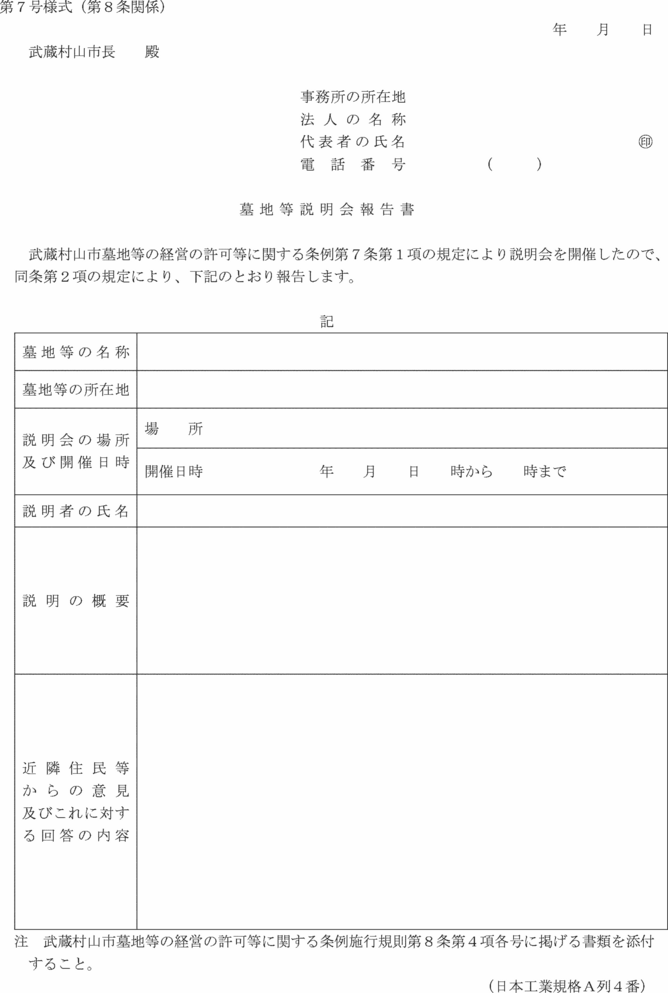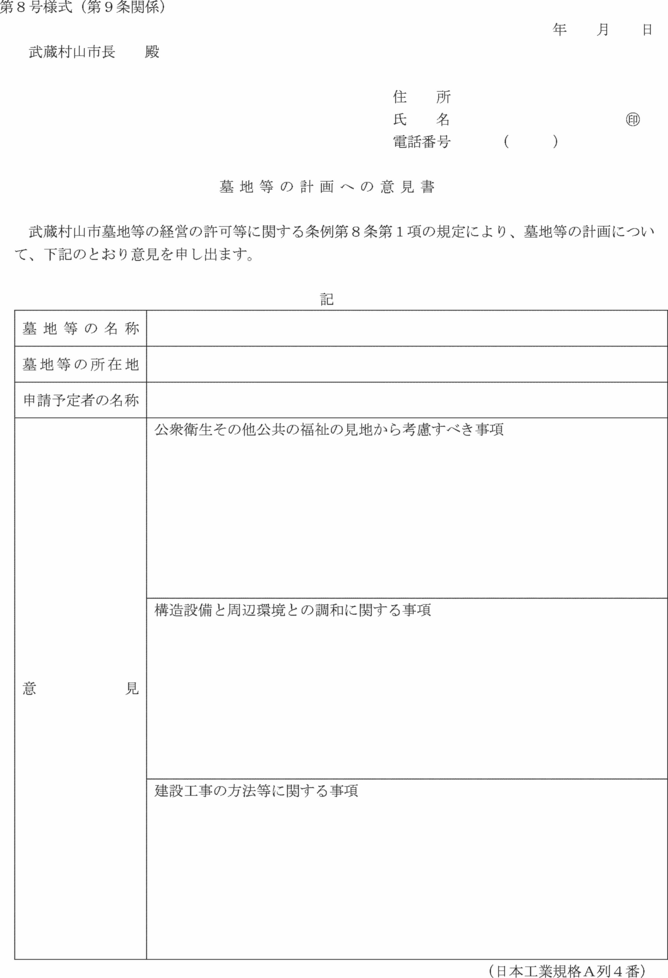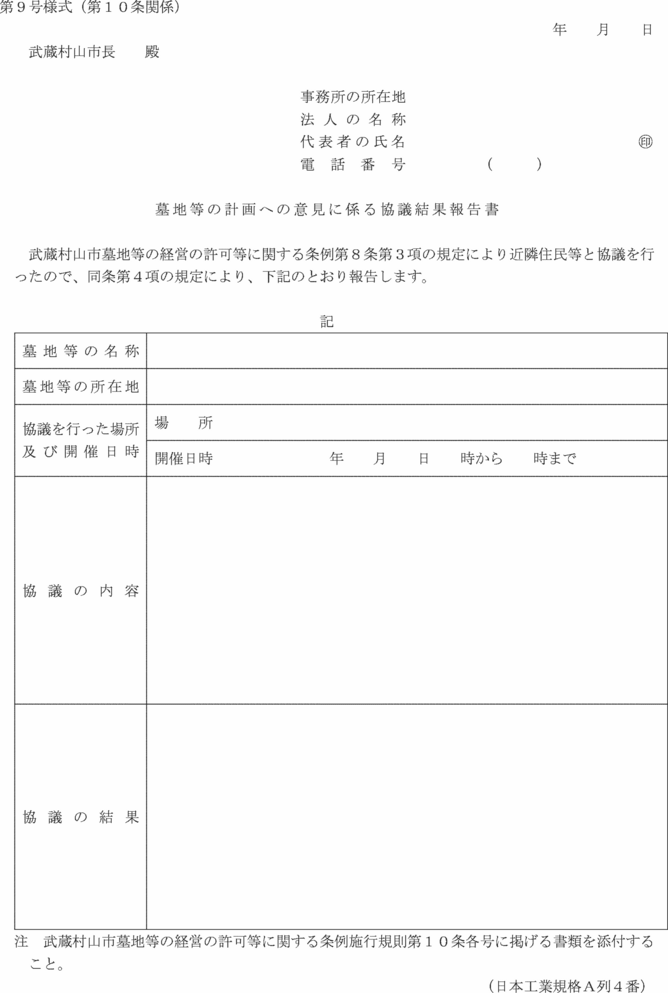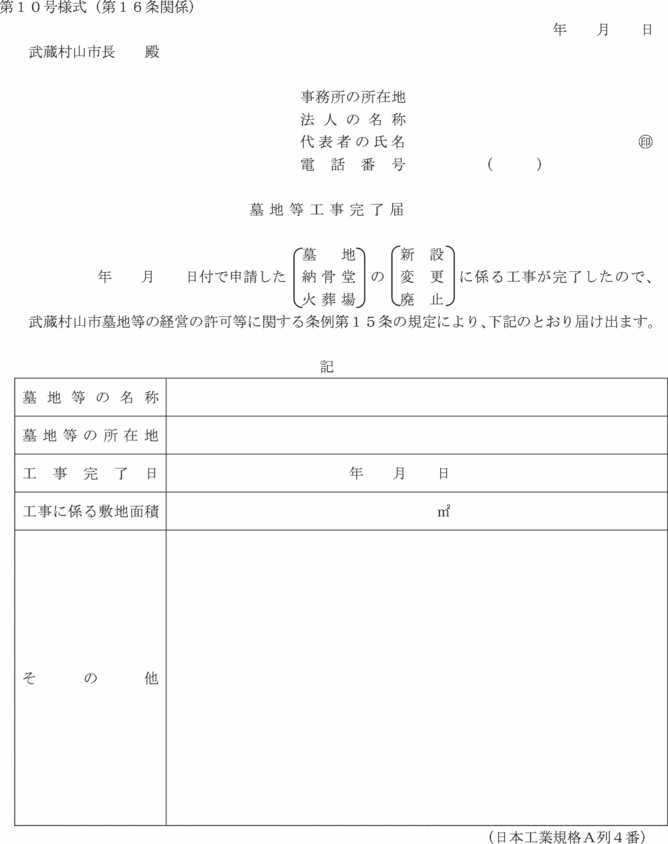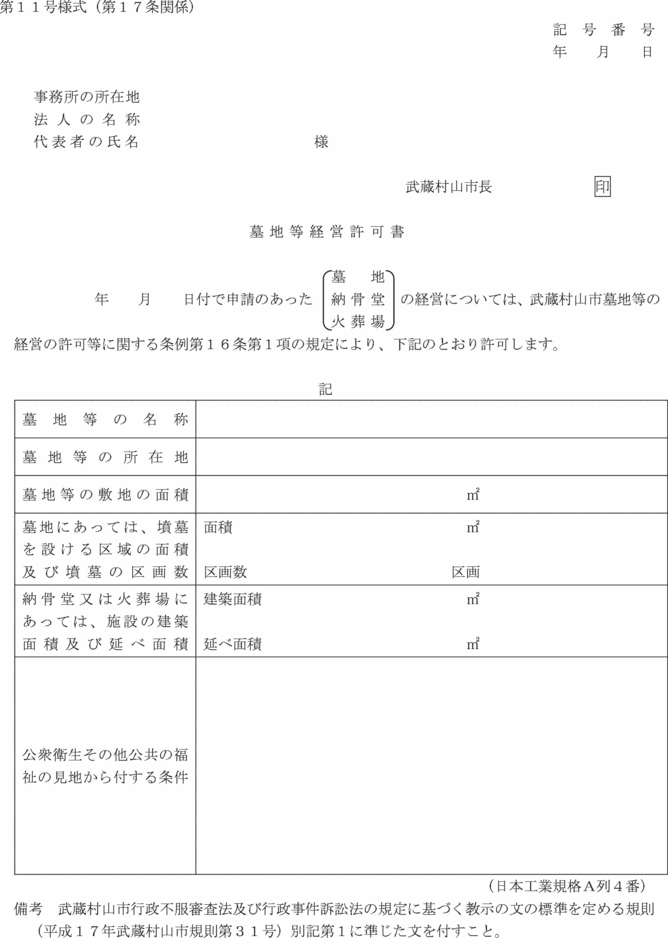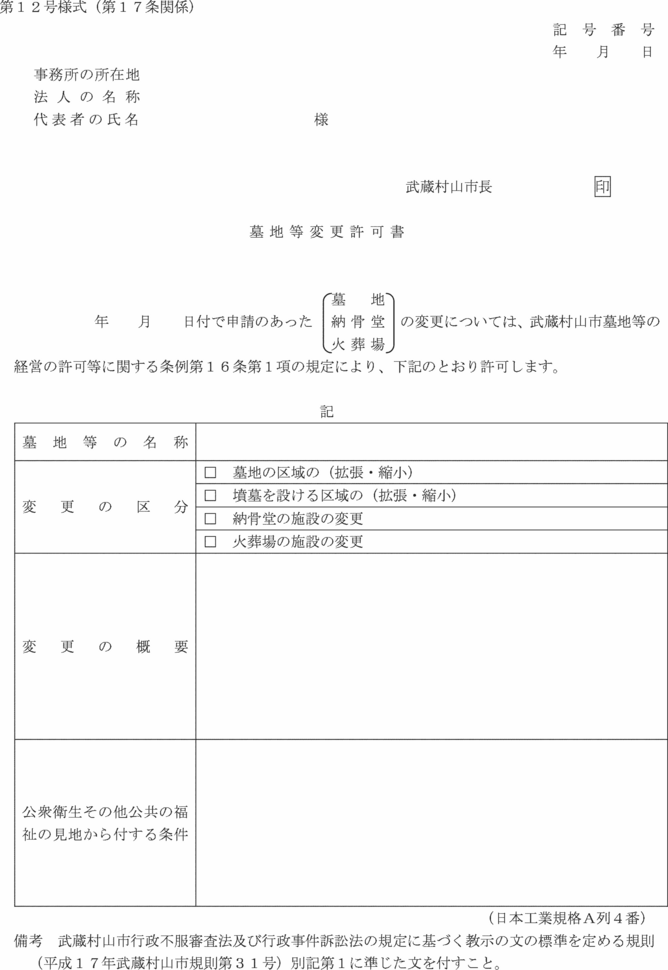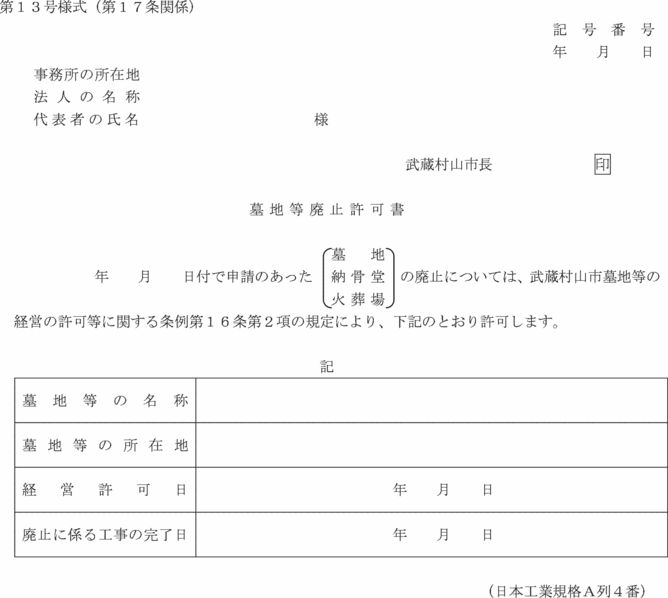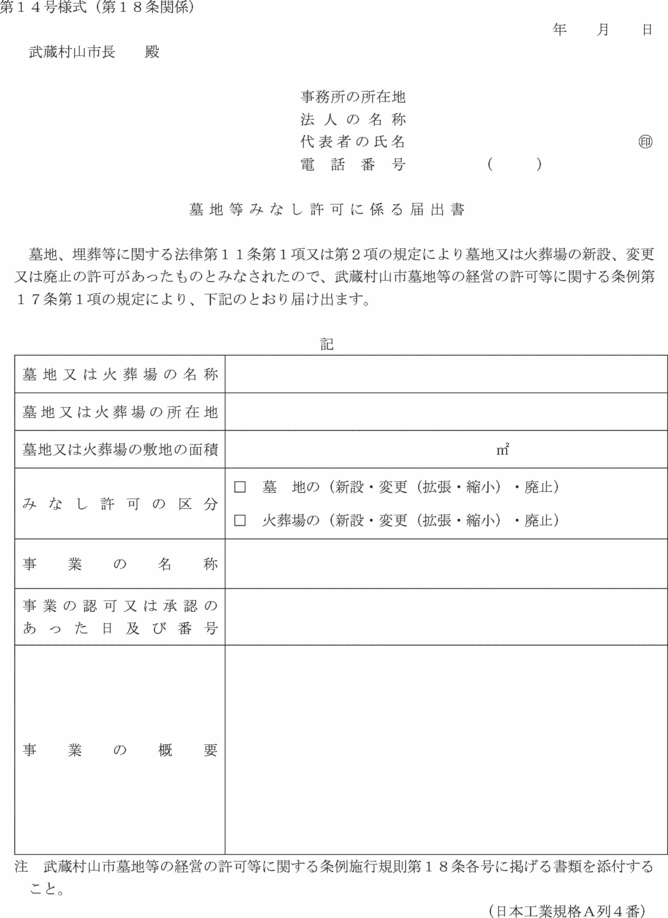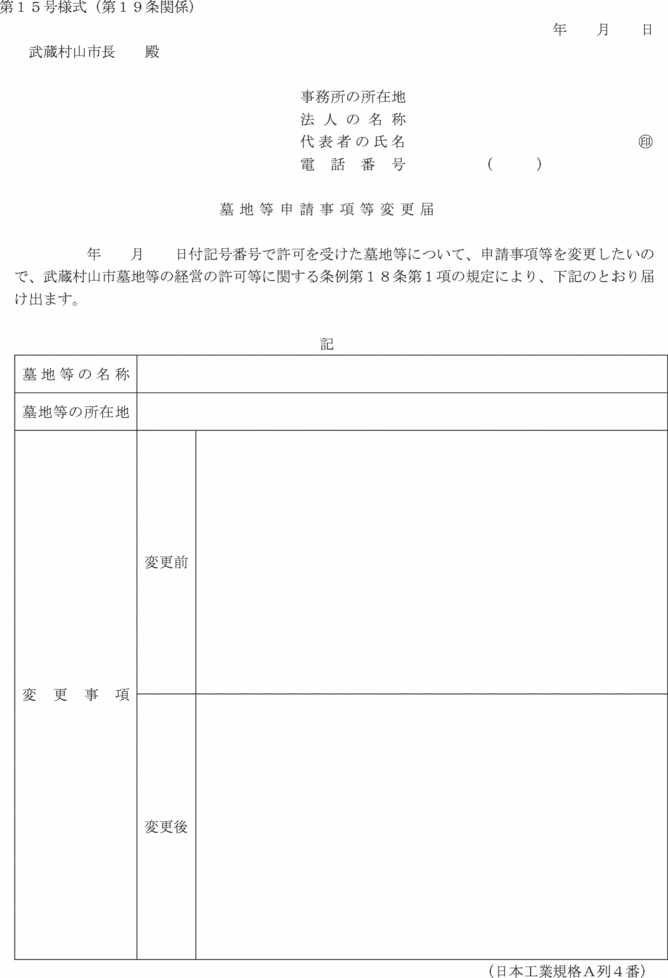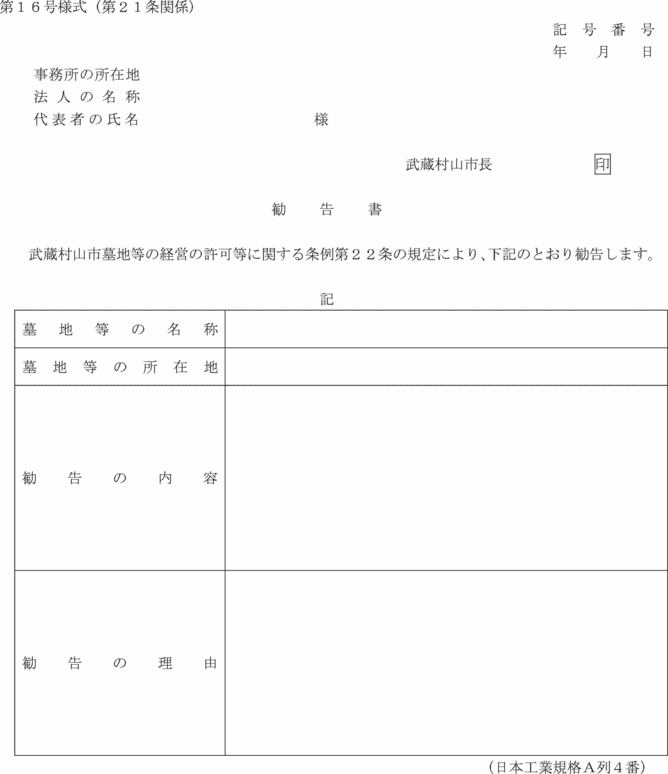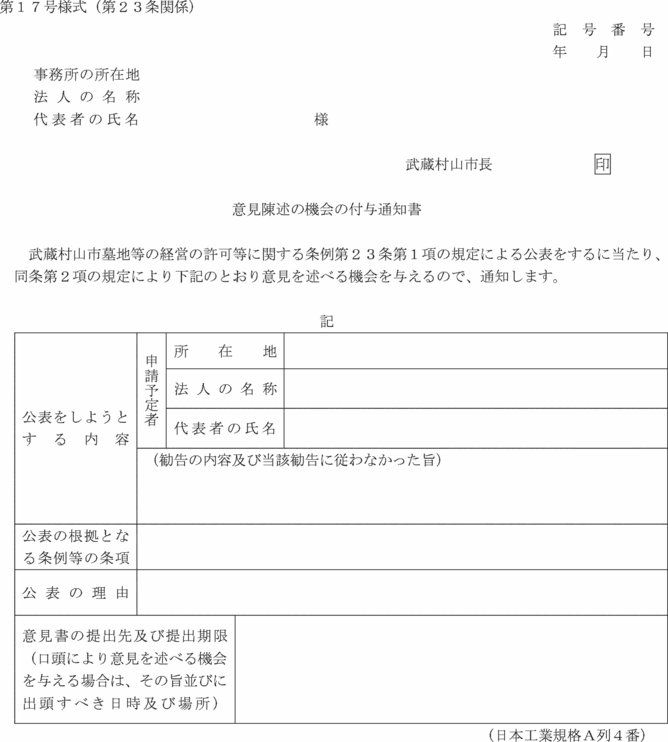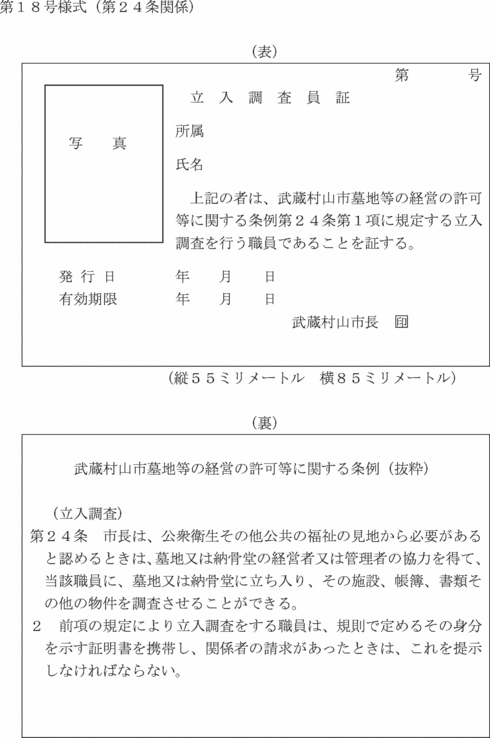○武蔵村山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月30日規則第12号
武蔵村山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、武蔵村山市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年武蔵村山市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(経営許可に係る申請)
(1) 墓地等の周囲300メートル以内の区域に存する道路、河川及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書
(4) 許可の申請に係る詳細な理由書
(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画書及び管理運営に係る書類
(7) 申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(8) 申請をしようとする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)による宗教法人である場合には、同法第12条第1項の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、当該規則に基づく当該申請に係る意思決定を示す書類、同法第25条第1項の財産目録及び収支計算書その他当該法人の財務状況を確認できる書類並びに当該法人の登記事項証明書
(9) 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類
(10) 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供する施設又は火葬場が存することを示す建物登記事項証明書
(11) 申請をしようとする者が条例第3条第1項第3号の公益法人である場合には、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに当該申請の意思決定の議事録
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更の許可に係る申請)
第4条 条例第4条第3項の規定による墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可の申請は、墓地等変更許可申請書(第2号様式)に前条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(廃止の許可に係る申請)
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書
(2) 当該廃止に係る第3条第4号及び第8号又は第11号に掲げる書類
(申請前協議書)
(標識)
2 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
3 申請予定者は、標識を、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、標識の記載事項が次項に規定する期間中鮮明であるように維持管理しなければならない。
4 標識は、申請予定日の90日前までに設置するとともに、条例第16条の許可の日まで設置しておかなければならない。
(1) 建設予定地の案内図
(2) 標識設置位置図
(3) 標識設置状況を撮影した写真
(説明等)
第8条 条例第7条第1項に規定する近隣住民等に対する説明会(以下「説明会」という。)は、申請予定日の60日前までに行わなければならない。
2 説明会においては、次に掲げる事項について説明しなければならない。
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地
(4) 建設予定地の面積並びに墓地等の建築面積及び構造設備の概要
(5) 墓地等の維持管理の方法
(6) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(7) 墓地等の工事の方法
(8) 条例第8条第1項による近隣住民等の意見の申出の方法
3 申請予定者は、説明会の開催日の7日前までに、近隣住民等に対し説明会の開催について通知しなければならない。
(1) 説明会において使用した資料
(2) 近隣住民等の名簿
(3) 説明会に出席した近隣住民等の名簿
(4) 建設予定地と隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等
(意見の申出)
(指導に基づく協議の報告)
(1) 協議に使用した資料
(2) 協議を行った者の名簿
(3) 協定等を締結した場合は、当該協定書等の写し
(障壁等の基準)
第11条 条例第10条第1項第2号の障壁又は密植した樹木の垣根の高さは、1.8メートル以上とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(自転車駐車場の基準)
第12条 条例第10条第1項第5号の規則で定める基準を満たす自転車駐車場は、墳墓の区画数の1パーセントに相当する数以上の自転車が駐車できるものとする。ただし、墓地の設置場所、周辺の状況等により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(緑地の基準)
第13条 条例第10条第1項第6号に規定する緑地は、樹木又は生垣により緑化したものとする。
2 前項の緑地には、条例第10条第1項第1号の規定により設けた緑地等の緩衝帯及び同項第2号の規定により設けた密植した樹木の垣根は含まないものとする。
3 樹木による緑化の面積の算出は、次の各号に掲げる緑化の方法の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した面積を合計することにより行うものとする。
(1) 樹木の植栽 次のアからウまでに掲げる樹木の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算出した面積の合計
ア 高木(通常の成木の樹高が3メートル以上の樹木で、植栽時に2メートル以上であるものをいう。) 1本につき3平方メートル
イ 中木(通常の成木の樹高が2メートル以上の樹木で、植栽時に1.2メートル以上であるものをいう。) 1本につき2平方メートル
ウ 低木(高木又は中木以外で、植栽時の高さが0.3メートル以上であるものをいう。) 4本程度を寄せ植えにしたもの1組につき1平方メートル
(2) 墓地等の区域内の既存樹木の存置又は移植 当該樹木ごとの樹冠(その水平投影面が建築物若しくは工作物の水平投影面と一致する部分又は事業区域外となる部分の樹冠を除き、他の樹冠の水平投影面と一致する部分については、いずれか1本の樹木の樹冠に限る。)の水平投影面積の合計
4 生垣による緑化の面積の算出は、生垣の長さに幅(0.6メートル未満のものにあっては、0.6メートルとする。)を乗じて得た面積として行うものとする。
(道路の基準)
第14条 条例第10条第1項第7号に規定する場合においては、当該道路の中心線から当該区域の方向への水平距離4.5メートルの線を境界線として、当該境界線から当該道路までの部分を道路として整備するものとする。
2 墓地の区域が接する道路がその中心線からの水平距離4.5メートル未満でがけ地、河川その他これに類するもの(以下「がけ地等」という。)に沿う場合における前項の規定の適用については、同項中「当該道路の中心線」とあるのは「がけ地等の境界線」と、「4.5メートル」とあるのは「9メートル」とする。
3 第1項の規定により整備する道路の構造は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 道路構造令(昭和45年政令第320号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準
(火葬場における自動車駐車場)
第15条 条例第14条第1項第9号の規則で定める数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
(1) 火葬場(次号に該当するものを除く。) 当該火葬場の火葬炉の数に10を乗じて得た数
(2) 斎場が併設されている火葬場 当該火葬場の火葬炉の数に30を乗じて得た数
(工事完了届)
(許可書)
(みなし許可に係る届出)
(1) 事業の認可書又は承認書の写し
(2) 事業計画書の写し
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要
(申請事項等の変更の届出)
(申請事項等の変更の届出を要しない場合)
第20条 条例第18条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる事項を変更しようとする場合とする。
(1) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(2) 前号に掲げるもののほか、軽易なものであると市長が認めるもの
(勧告)
(公表)
第22条 条例第23条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公告、武蔵村山市広報への掲載その他広く市民に周知できる方法により行うものとする。
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 申請予定者に対してした勧告の内容及び当該申請予定者がこれに正当な理由がなく従わなかった旨
(意見陳述の機会の付与の手続)
第23条 条例第23条第2項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出して行わなければならない。
2 市長は、意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述を認めたときは、その日時)までに相当な期間をおいて、意見陳述の機会付与通知書(第17号様式)により、当該意見陳述の機会を与える者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情がある場合には、意見書の提出期限の延長又は口頭により意見陳述を行う日時若しくは場所の変更を市長に申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を適当と認めたときは、意見書の提出期限を延長し、又は口頭により意見陳述を行う日時若しくは場所を変更するものとする。
5 市長は、第1項の規定により当事者に口頭による意見陳述を認めたときは、当事者が陳述した意見の要旨を記録するものとする。
(立入調査員証)
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。